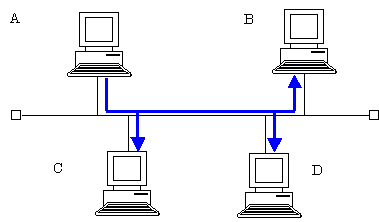| ãã�ã㸠ãã�ãã¸ã¨ã�ã®ã¯ããã�ã¯ã¼ã¯ã®æ¥ç¶å½¢æ ã§ãã�LANã§ã¯ããããã¸ã¨ãã¦æ¬¡ã®�ã¤ã代表ç�ªãã�ã§ãã� ã»ãã¹å� ãã¹åã�ãä¸å¿�¨ãªãã±ã¼ãã«�å軸ã±ã¼ãã«�ã«ã³ã³ãã¥ã¼ã¿ãã�ãããããããªæ¥ç¶å½¢æ ã§ãã� 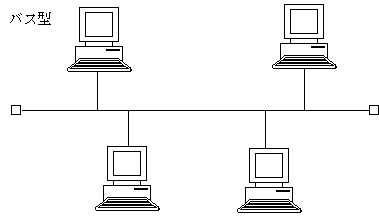 ã»ã¹ã¿ã¼å� ã¹ã¿ã¼åã�ããããä¸å¿�¨ãã¦å�³ã³ãã¥ã¼ã¿ãæ¥ç¶ããå½¢ã«ãªãã¾ãã� 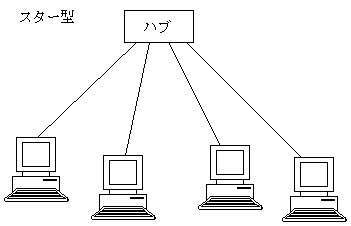 ã»ã¹ã¿ã¼ãã¹å� ã¹ã¿ã¼åã�ãããè¤�°æ¥ç¶ããæ¥ç¶å½¢æ ãã¹ã¿ã¼ãã¹åã¨ã�ã¾ãã� 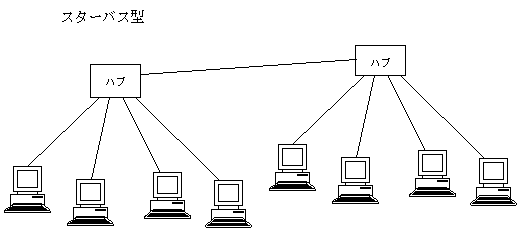 ã»ãªã³ã°å� ã³ã³ãã¥ã¼ã¿ã輪ãä½ããããªæ¥ç¶å½¢æ ããªã³ã°åã§ãã� 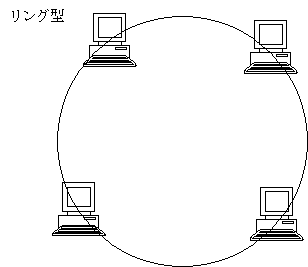 ãã�ããã«ãã�ãã¸ãããã¤ãããã�ã§ãããLANã®è¦æ�¼ã«ãã£ã¦å©ç¨ããããããã¸ã決ã¾ã£ã¦ã�¾ãã�
|