Table of Contents
レイヤ3スイッチの役割
レイヤ3スイッチは、VLANによってネットワーク構成を柔軟に決めることができ、主に企業ネットワークで複数のネットワークを相互接続するために利用します。
レイヤ3スイッチは、レイヤ2スイッチにルータの機能を追加しているネットワーク機器です。そのため、レイヤ2スイッチのようなデータの転送もできますし、ルータのようなデータの転送もできます。レイヤ3スイッチの外観は、レイヤ2スイッチとよく似ています。レイヤ2スイッチと同じようにたくさんのイーサネットインタフェースを備えたネットワーク機器です。ただ、レイヤ2スイッチに比べると、レイヤ3スイッチはかなり高価です。そのため、レイヤ2スイッチとして利用するだけなら、レイヤ2スイッチを使ったほうがコストを抑えられます。
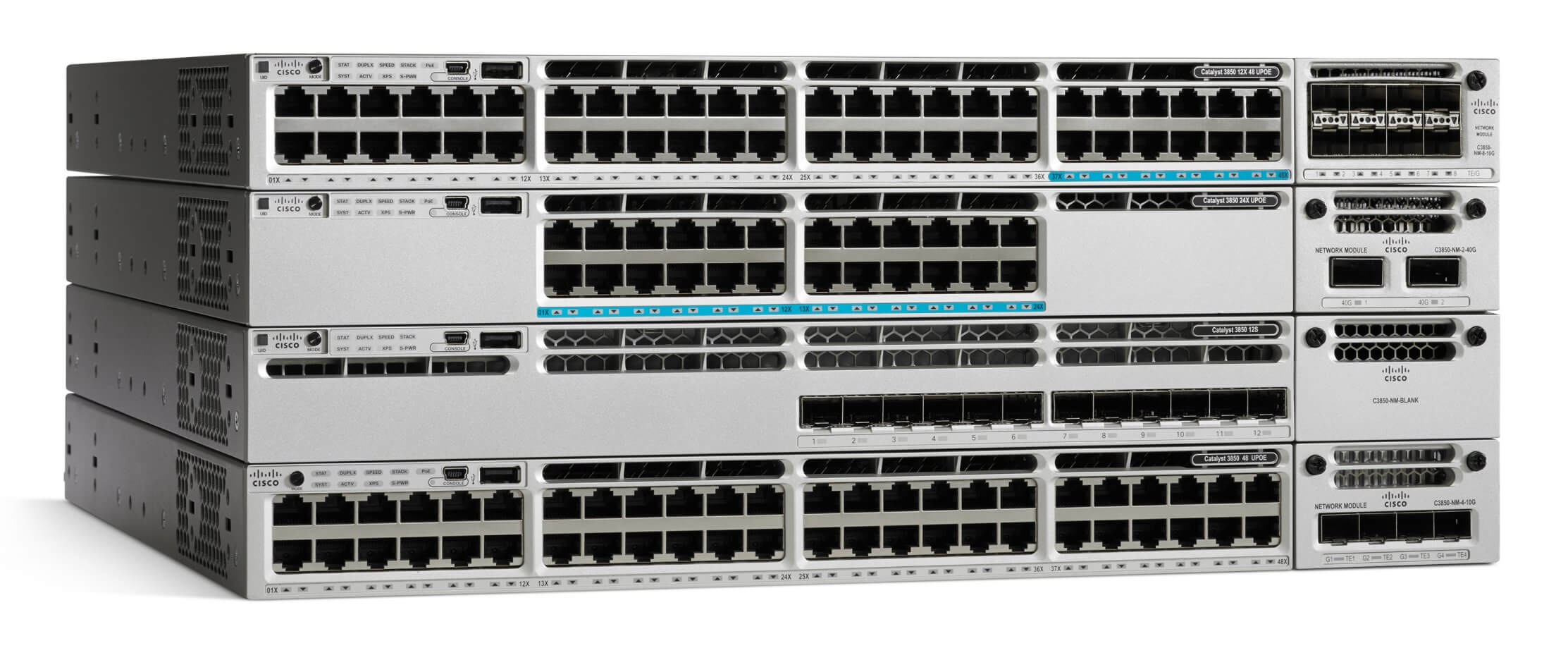
外観はレイヤ2スイッチと同じなのですが、レイヤ3スイッチは基本的な機能としてルータと同等です。すなわち、レイヤ3スイッチによってネットワークを相互接続して、ネットワーク間のデータを転送します。レイヤ3スイッチを利用すれば、1台でVLANによりネットワークを論理的に分割して、分割したVLANを相互接続できます。そして、相互接続したVLAN間でデータを転送します。
レイヤ3スイッチのデータの転送は、同じネットワーク内か異なるネットワーク間かによって、振る舞いが違います。同一ネットワークのデータの転送のときはレイヤ2スイッチ同じようにMACアドレスに基づいて転送します。一方、ネットワーク間のデータ転送のときはルータと同じようにIPアドレスに基づいてデータの転送を行います。
ここで、レイヤ2スイッチとルータのデータの転送の特徴をあらためて以下の表にまとめています。
| 特徴 | レイヤ2スイッチ | ルータ |
|---|---|---|
| 転送対象のデータ | イーサネットフレーム | IPパケット |
| データの転送範囲 | 同一ネットワーク内 | ネットワーク間 |
| 転送するときに参照するテーブル | MACアドレステーブル | ルーティングテーブル |
| 転送するときに参照するアドレス | MACアドレス | IPアドレス |
| テーブルに必要な情報がないときの動作 | データをフラッディング | データを破棄 |
以下の図は、レイヤ3スイッチでネットワークを相互接続している様子と、データの転送についてまとめたものです。
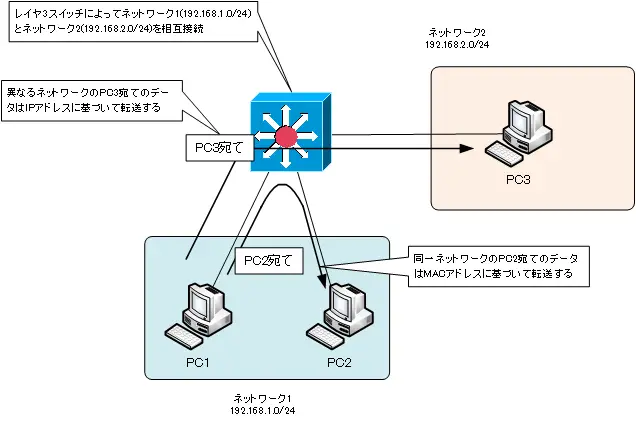
この図で、レイヤ3スイッチはネットワーク1(192.168.1.0/24)とネットワーク2(192.168.2.0/24)を相互接続しています。そして、PC1とPC2は同じネットワークとなり、PC3は違うネットワークとしています。このようなネットワーク構成を取るために、レイヤ3スイッチでVLAN(Virtual LAN)の機能を利用します。レイヤ3スイッチの仕組みを知る上では、VLANを理解することが必須です。
VLANを理解することがレイヤ3スイッチの仕組みを知るためにとても重要
レイヤ3スイッチとルータ
前述のように、レイヤ3スイッチとルータは基本的な機能は同等ですが、異なる点もあります。レイヤ3スイッチとルータの違いを簡単にまとめます。
| 特徴 | ルータ | レイヤ3スイッチ |
|---|---|---|
| インタフェースの種類 | イーサネット以外にもいろんなインタフェースを利用可能 | 基本的にイーサネットのみ |
| インタフェースの数 | それほど多くの数のインタフェースを備えていない | 製品によっては数百以上の数のインタフェースを備えている |
| データの転送性能 | あまり高くない | 理論的な最大の転送性能を発揮できる |
| サポートする機能 | VPNやファイアウォールなどの追加機能をサポートしている製品が多い | 基本的にデータを転送する機能に特化している |
ただ、この表にまとめたルータとレイヤ3スイッチの違いの大部分はほとんどなくなっています。
レイヤ3スイッチにも製品によって、イーサネット以外のインタフェースを搭載できるものも増えています。イーサネットインタフェースだけで用が足りることがほとんどなので、対応するインタフェースの種類はあまり問題になりません。
たくさんのイーサネットインタフェースを備えたルータも増えています。Ciscoのルータにイーサネットスイッチモジュールを追加すれば、イーサネットインタフェースの数を増やせます。ルータをレイヤ3スイッチとして利用することも可能です。
また、ルータのデータの転送性能も高くなってきていて、理論的な最大の転送性能を発揮できる製品も多くあります。
ルータとレイヤ3スイッチの大きな違いは、サポートする追加機能です。ルータは単にネットワーク間のデータを転送する以外にVPNゲートウェイ、ファイアウォール機能などのさまざまな機能をサポートしている製品が多くあります。一方、レイヤ3スイッチは製品によってはルータと同じようにVPNゲートウェイ/ファイアウォールなどのいろんな機能を使えるものもあります。ですが、基本的には高速なネットワーク間のデータを転送する機能に特化しています。
社内ネットワーク(LAN)の構成
企業の社内ネットワークは、レイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチ、そしてルータで構成します。それぞれをどのように利用しているかをまとめておきましょう。
- レイヤ2スイッチ/レイヤ3スイッチ:社内ネットワーク(LAN)を構築する
- ルータ:社内ネットワーク(LAN)をWANやインターネットなどの外部ネットワークへ接続する
オフィスのフロアのクライアントPCはまず、レイヤ2スイッチに接続します。ネットワークの入り口に相当するレイヤ2スイッチは「アクセススイッチ」と呼ばれます。PCなどに社内ネットワークへのアクセスを提供するのでアクセススイッチです。アクセススイッチでVLANによって、ネットワークを分割します。
そして、フロアのレイヤ2スイッチを集約するためにレイヤ3スイッチを利用します。レイヤ3スイッチでは、アクセススイッチで作成してるVLANを相互接続して、VLAN間の通信ができるようにします。フロアのアクセススイッチを集約するレイヤ3スイッチは「ディストリビューションスイッチ」と呼ばれます。「ディストリビューション」は英単語の「distribution」をカタカナ表記しているだけです。「distribution」は、「配布する」とか「分配する」という意味です。ネットワーク間のデータを配布(分配)する、つまり、ネットワーク間の通信を実現するためのスイッチという意味です。
アクセススイッチとディストリビューションスイッチで1つの建物のネットワークを構成します。大規模な社内ネットワークであれば、1つの拠点の敷地内に複数の建物が存在します。当然ながら、建物のネットワーク同士も相互接続しなければいけません。建物のネットワークの相互接続にもレイヤ3スイッチを利用します。こうした建物のネットワーク間の相互接続のためのレイヤ3スイッチは「コアスイッチ」または「バックボーンスイッチ」と呼ばれます。建物間のデータやWAN/インターネット宛てのデータが通る中心となるスイッチなので「コア」または「バックボーン(背骨)」という呼び方がされています。
このように、ある拠点の社内ネットワーク、すなわち、LANはレイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチを組み合わせて構築します。
そして、拠点が複数箇所ある場合は各拠点のLANは、WANによって相互接続します。WANに接続するためには、一般的にルータを利用します。今ではWANへの接続にもイーサネットインタフェースを利用できるようになっていますが、以前はWANに接続するためにはシリアルインタフェースやATMインタフェースといったイーサネット以外のインタフェースを利用することがほとんどだったからです。
また、多くの場合、拠点のLANをインターネットにも接続することでしょう。インターネットへの接続もルータを利用することが一般的です。ルータの追加のファイアウォール機能やVPNゲートウェイ機能などを利用するためです。
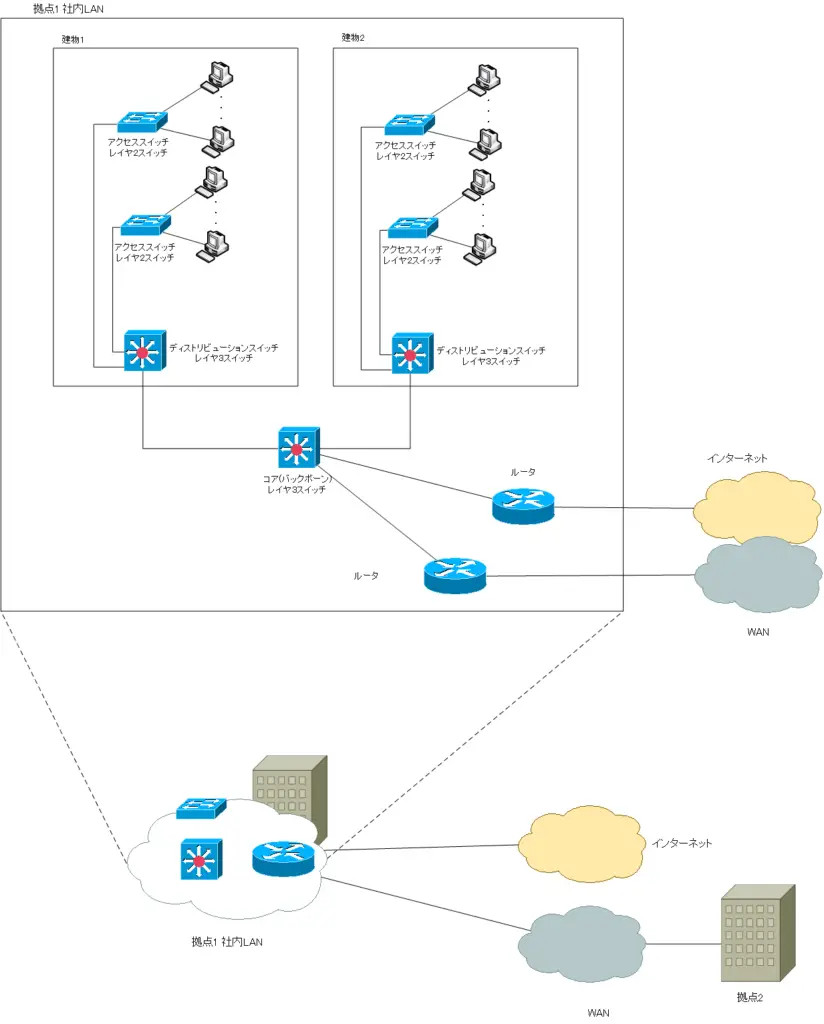
まとめ
ポイント
- レイヤ3スイッチは、レイヤ2スイッチにルーティングの機能を追加したネットワーク機器です。
- ルータもレイヤ3スイッチも基本的なネットワークを相互接続して、ネットワーク間の通信を行うという機能は同じです。
- 企業の社内ネットワークは主にレイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチ、ルータで構築します。
- レイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチでLANを構築します。そして、構築したLANをWAN/インターネットに接続するためのルータを利用します。
IPルーティングのキホン
- ルータ ~ルーティングを行う中心的な機器~
- ルータでネットワークを分割
- レイヤ3スイッチ
- ルーティングの動作
- ルーティングテーブル
- ルーティングテーブルの作り方
- ホストルート ~/32のルート情報~
- スタティックルーティング?それともダイナミックルーティング? ~設定の考え方の違い~
- スタティックルーティングとダイナミックルーティング(RIP)の設定の比較
- スタティックルートのメリット・デメリット
- ルーティングプロトコルのメリット・デメリット
- ルート情報をアドバタイズする意味
- 宛先ネットワークまでの距離を計測 ~アドミニストレイティブディスタンスとメトリック~
- 等コストロードバランシング
- ルート集約 ~まとめてルーティングテーブルに登録しよう~
- デフォルトルート ~究極の集約ルート~
- 最長一致検索(ロンゲストマッチ) ~詳しいルート情報を優先する~
- インターネットのルート情報を見てみよう AT&T Looking Glass
- ルーティングプロトコルの分類 ~適用範囲~
- ルーティングプロトコルの分類 ~アルゴリズム~
- ルーティングプロトコルの分類 ~ネットワークアドレスの認識(クラスフルルーティングプロトコル/クラスレスルーティングプロトコル)~
- Cisco スタティックルートの設定
- ip default-network ~特定のルート情報に「*」をつける~
- スタティックルートをバックアップに ~フローティングスタティック~
- スタティックルートの設定を一歩ずつわかりやすく行う設定例[Cisco]
- Ciscoスタティックルーティングの設定例
- IPルーティング基礎演習Part1
- IPルーティング基礎演習Part2
- IPルーティング基礎演習Part3
- Windows PCのスタティックルートの設定 route addコマンド
- RIPの概要
- RIPの動作 ~RIPルート情報を定期的に送りつける~
- RIPスプリットホライズン
- RIPタイマ
- RIPルートポイズニング ~不要なルート情報を速やかに削除~
- Cisco RIPの設定と確認
- Cisco RIPの設定例
- RIPでのデフォルトルートの生成 ~スタティックルートの再配送~
- RIPでのデフォルトルートの生成 ~default-information originate~
- RIPでのデフォルトルートの生成 ~ip default-network~
- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part1
- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part2
- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part3
- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part4
- パッシブインタフェース(passive-interface) ~ルーティングプロトコルのパケット送信を止める~
- 転送経路を決定する方法 ~アドミニストレイティブディスタンス/メトリックと最長一致検索~
- デフォルトゲートウェイの詳細 ~ホストもルーティングしている~
- デフォルトゲートウェイの冗長化の概要
- Cisco HSRPの仕組み
- Cisco HSRP 仮想ルータ宛てのパケットがアクティブルータへ転送される仕組み
- Cisco HSRPトラッキング ~より柔軟にアクティブルータを切り替える~
- Cisco HSRP設定と確認
- Cisco HSRPの負荷分散
- HSRP 設定ミスの切り分けと修正 Part1
- VRRPの仕組み
- VRRPの設定と確認コマンド [Cisco]
- ルーティングテーブルのトラッキング(Cisco HSRP/VRRP)
- Cisco HSRP ルーティングテーブルのトラッキング設定例
- VRRP ルーティングテーブルのトラッキング設定例
- GLBPの仕組み
- Cisco GLBPの設定と確認
- Cisco GLBPの設定例
- HSRP/VRRP/GLBPのアドレス情報のまとめ

